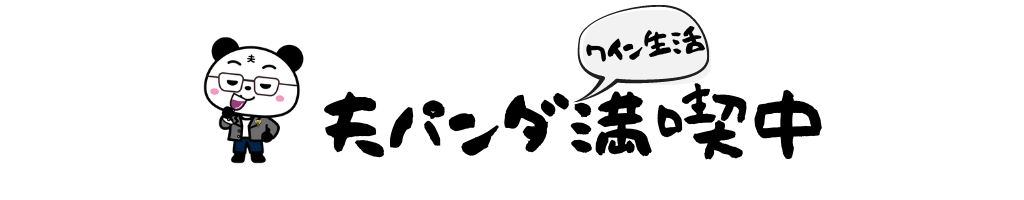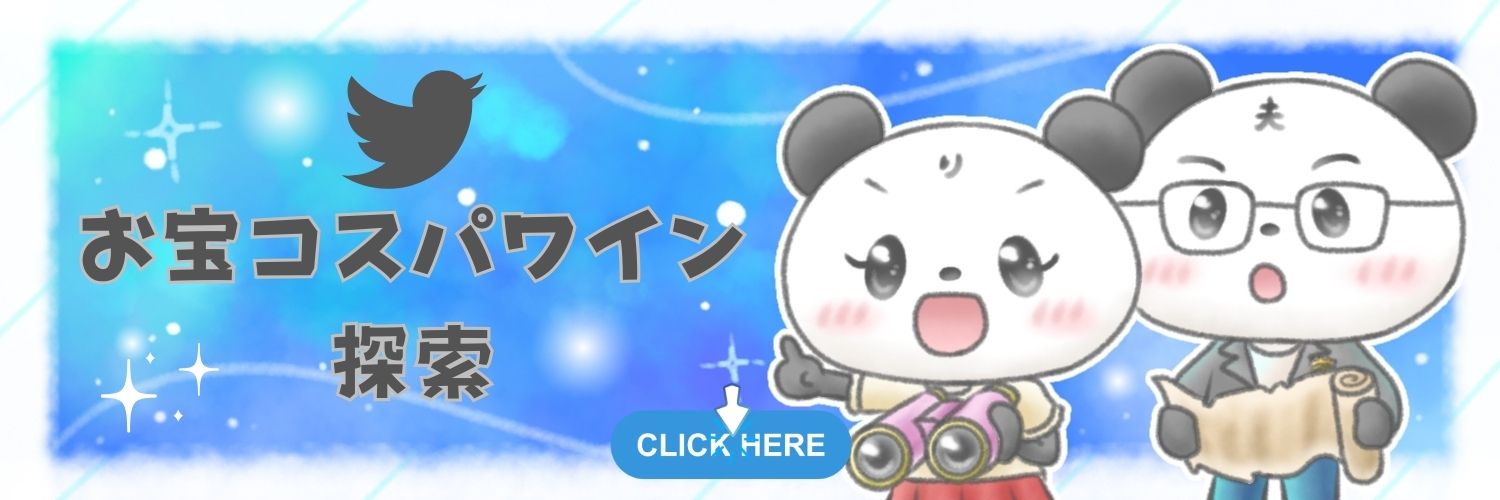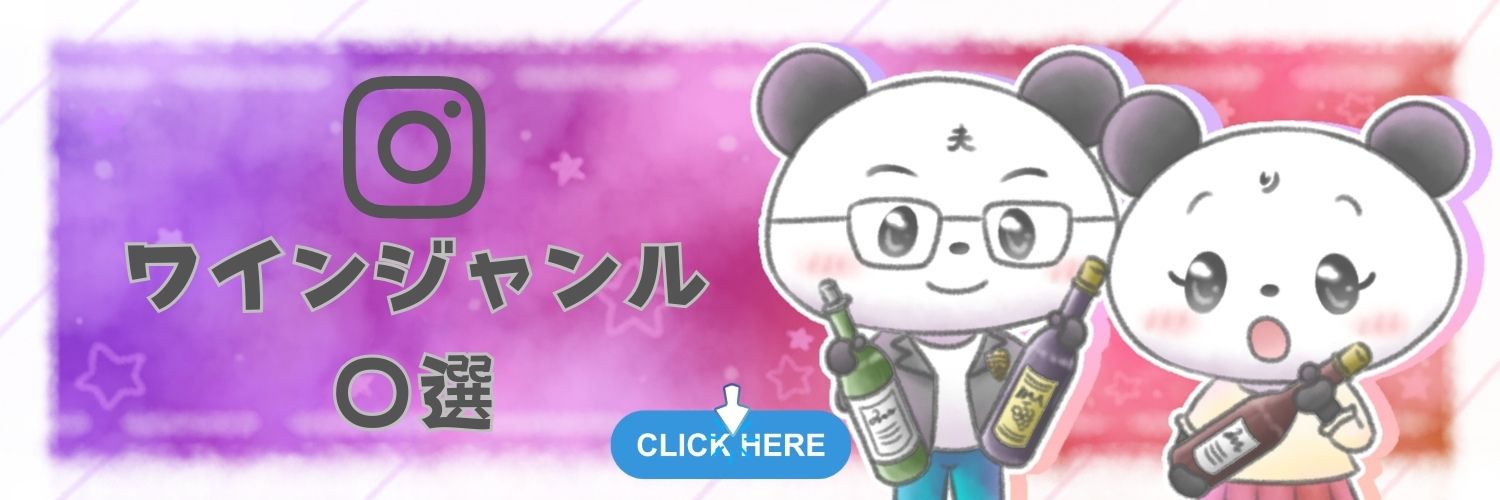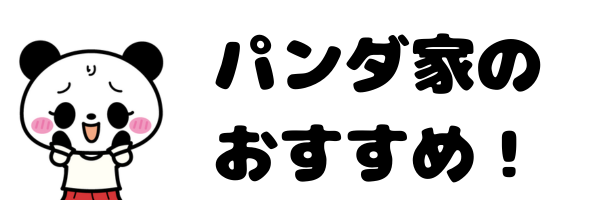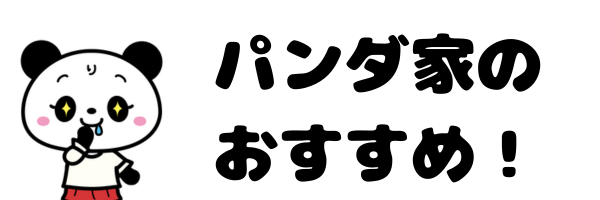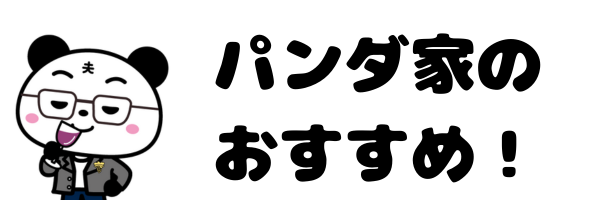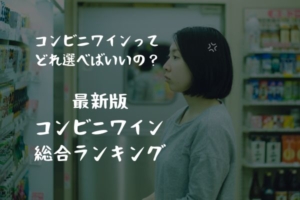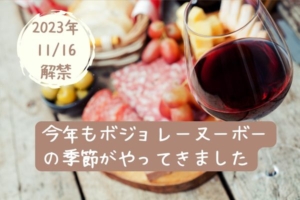記事内に広告を含みます
ワインダイエット?!美容にも効果的なワインのカロリーや効能について徹底解説!

 りえパンダ
りえパンダ今、ダイエット中なんだけど、ワインって太りやすいのかな?



今回はワインの効用について整理しました。もしよければ最後までお付き合いください。
目次
ワインは太るのか?


「ワインは太るのか?」という疑問について、多くの人が気になることでしょう。しかし、実際のところ、ワインを適量飲むことは、健康に良い影響を与えることが研究によって示されています。
一般的に、ワインで太ることはありません。むしろ、ワインを適度に飲むことは、心血管疾患や糖尿病のリスクを減らし、炎症や悪玉コレステロールを低下させるという研究結果があります。また、ワインにはポリフェノールや抗酸化物質が含まれており、美容やアンチエイジングにも効果的とされています。
もちろん、飲み過ぎは悪影響を与えることがあります。ワインに含まれるアルコールは、摂取量を過ぎると肝臓に負担をかけ、肝臓疾患や膵炎などの疾患を引き起こす可能性があります。また、カロリーも気になるところですが、一般的にグラス1杯のワインは120~125キロカロリー程度と、他のアルコール飲料に比べて低カロリーです。
適度なワインの消費は、健康全般に有益であり、太る心配はありません。しかし、自分の体調や健康状態をよく理解し、常に節度ある飲酒を心がけることが大切です。ワインを飲むときは、自分に必要な量を理解し、適切なバランスを見つけることが、健康的で楽しいワインライフを送るためには必要なことです。
主要なお酒のカロリー比較
主要なお酒の100mlあたりのカロリー比較です。
- ビール:40〜60kcal
- ワイン(赤/白):120〜130kcal
- 日本酒:140〜150kcal
- 焼酎:200〜240kcal
- ウイスキー:220kcal
お酒にはカロリーが含まれることは知っていますが、実はお酒の種類によってカロリーが異なることをご存知ですか?
例えば、アルコール度数が高いお酒は同じ量でもカロリーが多くなります。つまり、焼酎やブランデーはアルコール度数が高く、同じ量のワインと比べるとカロリーが高くなる傾向があるのです。それに対して、ワインはアルコール度数が低いため、同じ量でも比較的カロリーが低くなります。
また、お酒に含まれる糖分もカロリーに影響します。ワインに含まれる糖分は比較的少なく、ビールやカクテルに含まれる糖分が多いため、それらと比較してもカロリーが低くなる傾向があります。
ただし、ワインにも種類によってカロリーが異なる場合があるため、注意が必要です。甘口のワインは糖分が多く、カロリーも高くなります。また、ワインの生産方法や産地によってもカロリーが異なる場合があるため、気になる方はラベルをよくチェックしましょう!
日本食品標準成分表2020年度版によると、赤ワインは約1杯82Kcalに対して白ワインは約1杯90Kcalとのことで、ワインのタイプにもよりますが一般的には赤ワインより白ワインの方が若干カロリーが高めです。
ワインの糖質量
お酒に含まれるカロリーについて、蓄積しにくいエンプティカロリーとも言われますね。これは意外な事実かもしれませんが、確かにお酒に含まれるカロリーは体に蓄積されにくい傾向があります。ただし、これは飲み過ぎによるアルコール中毒や肝臓の負担など、健康に悪影響を与えるリスクがあることも忘れてはいけません。
そこで、太りやすいかどうかを気にする場合には、お酒に含まれるカロリーよりも糖質の量を意識する必要があります。というのも、糖質が多く含まれているお酒は、摂りすぎると血糖値の急上昇を引き起こすため、脂肪を蓄積しやすくなると言われているからです。
主要なお酒の糖質量の比較です。
- ハイボール1杯(約3350ml) 0g
- ワイングラス1杯(約120ml) 約2g
- ビール中ジョッキ1杯(約350ml) 約13g
- 日本酒1合(約180ml) 約7.8g
- 梅酒1杯(約200ml) 約41g
蒸留酒(ウイスキー、ブランデー、焼酎)は基本的に0gということはご存知でしょうか?
そう、ハイボールもサワーも糖質0gなんです!ただし、サワーには果汁が加わるため、加えた分の糖質が糖質量になってしまいます。特にカルピスサワーは要注意ですね!
一方、醸造酒(ワイン、ビール、日本酒)には糖分が含まれています。中でも、ワインは最も糖分が少ないお酒です。実は、ワインは蒸留酒の中でも太りにくいお酒なんです!
ワインのお供、チーズが太る?
「ワインのお供といえば、やっぱりチーズでしょ!」って思われる方も多いのではないでしょうか?
でも、チーズって高カロリーで太るんじゃないかって思われることもあるかもしれません。
ですが、実はチーズにはダイエット中に不足しがちな「タンパク質」と「カルシウム」がたっぷり含まれているんですよ。これって、健康的なダイエットの手助けにもなってくれるんです。さらに、脂質や糖質の代謝を促進する「ビタミンA」と「ビタミンB2」もたっぷり含まれているんです。
ですので、実はチーズって、少量ならダイエットにもってこいの食材なんですよ。思い切って、チーズをワインのお供に選んで、美味しく健康的なダイエットを楽しみましょう!
寝る前のワインにダイエット効果あり?
知ってましたか?ハーバード大学の調査で、寝る前に赤ワインを飲むと脂肪燃焼効果がアップするっていうんです!
毎日、寝る前にグラス1~2杯の赤ワインを飲む女性は、肥満になる確率が低くなったって報告されているそうですよ。
しかも、ワインを飲むことで血行が促進され、暖かい状態で眠れるので、冷え太りも予防できるかも!
もちろん、飲みすぎはよくありませんが、適量の1~2杯なら安心ですね。
今夜から、寝る前のワインタイムを取り入れて、健康的なダイエットを楽しんじゃいましょう!
ワインの美容効果は?


ワインが美容に良いという話も1度は聞いたことがあるのではないでしょうか。ここでは改めてワインの美容効果を整理してみました。
ワインの血行促進効果
また、ワインに含まれるアルコールも、適度な量であれば血管を拡張させる効果があるとされています。血管を拡張させることで、血流がスムーズになり、血行が促進されます。
ワインのアンチエイジング効果
ワインを飲むことでアンチエイジング効果があるのは、皆さんもよく聞いたことがあるかもしれませんね。その理由について詳しく見ていきましょう!
まず、ワインに含まれるポリフェノールが注目されています。ポリフェノールには、抗酸化作用があり、体内の活性酸素を除去することができます。活性酸素は、老化や生活習慣病の原因となることがあるので、ワインを飲むことで体内の活性酸素を減らすことができ、アンチエイジングにつながるのです。
また、ワインに含まれるレスベラトロールという成分にも注目が集まっています。レスベラトロールには、紫外線から肌を守る効果があると言われています。さらに、血管を拡張させる効果があるため、血行を促進して、肌のターンオーバーを促進する効果も期待されます。
ワインのデトックス効果
ポリフェノールはブドウの果皮などに含まれる成分のため、果皮を使わない白ワインにはポリフェノールはあまり多く含まれません(全く含まれないわけではありません)。
しかし、白ワインには有機酸が豊富に含まれます。有機酸は腸内環境を整える作用があるといわれており、お肌の大敵である便秘解消などの効果があるといわれております。
また、白ワインにはカリウムも豊富に含まれます。カリウムには利尿作用があり、余分な水分や老廃物が外に排出されるのでむくみ防止、デトックス効果があるそうです。
ワインの健康への効能は?


フランス人は他の西欧諸国にくらべて喫煙率などが高いにもかかわらず、心臓病等による死亡率が低いという事実があります。
この現象は”フレンチ・パラドックス”と呼ばれ、フランス人のワイン摂取量の多さが要因ではないかと言われています。実際この”フレンチ・パラドックス”については完全には解明されておらず批判的な研究者もいます。
しかし、ワインが健康に良い効果があるのも事実の様ですので、ここでは一般的に多く言われているワインが健康に与える良い効果をご紹介します。
血糖値を抑える
赤ワインに多く含まれるポリフェノールには血糖値を抑える効果がある可能性が高いという研究結果があります。
認知症(アルツハイマー)防止
赤ワインに多く含まれるとポリフェノールの一種であるレスペラトロールいう成分は、認知症の予防になると考えられています。アメリカの大学の実験では、日々のワイン摂取とアルツハイマー発症率に相関関係があることが確認されたそうです。
動脈硬化の防止
動脈硬化の原因は悪玉コレステロールが酸化することによるものですが、赤ワインに多く含まれるポリフェノールの抗酸化作用により悪玉コレステロールの酸化を妨げる効果があるといわれています。
癌予防の効果
赤ワインに多く含まれるポリフェノールの一種であるレスペラトロールは抗癌作用があり、癌細胞が増えるのを防ぐ効果があるといわれています。また、プロアントシアニジンという成分は、乳癌の予防に効果があるともいわれています。
ワインのベストな飲み方は?
一日に飲む適量は?
どの文献や書籍でも共通して言われていることは、飲みすぎてはいけないということです。
いかに良い効用があるワインとはいえ、飲み過ぎれば必ず身体に悪影響がでます。
1日あたりワイングラス2杯ぐらいが適量というのが大方の意見です。
ワインボトル1本でおおよそワイングラス6杯分になりますので、一人で飲む場合はワインボトル1本を3日で飲み切るペース、パートナーがいる場合は3日でワインボトル2本のペースがベストということになります。
ワインはワインボトルの栓を開けると酸化が始まり味が低下します。しかし、1週間程度であれば問題ありません。ワインの酸化を抑えるワインボトル専用の栓も安価で売られていますので、そういったものを購入されるのも良いかと思います。
ダイエット向けワインレシピ 「しょうがワイン」



しょうがに含まれるショウガオールが体を温め、新陳代謝を促し、脂肪が燃焼しやすい体にしてくれるそうです。
【材料】1杯分
白ワイン 1/2カップ
しょうがの薄切り 10枚
湯 1/2カップ
【作り方】
1.耐熱皿にしょうがを並べ、電子レンジで3~4分加熱する。
2.グラスに1を好きな分量入れて湯を入れ、ワインを注ぐ。
アンチエイジング向けワインレシピ 「ブルーベリーフェズ」



ブルーベリーは血がドロドロの状態に働きかけてくれるそうです。クマやシミ、くすみにも良いみたいです。
【材料】1杯分
赤ワイン 1/2カップ
ブルーベリージャム 大さじ2
酢 小さじ2
【作り方】
グラスにブルーベリージャム、酢を入れて混ぜ合わせ、ワインを注ぐ。
おわりに


今回はワインの素晴らしい効果についてお伝えしてきましたが、最後に悪い効果についても少し触れておきたいと思います。
ポリフェノールには血流促進や血管拡張作用があるため、頭痛持ちの方には頭痛を引き起こすことがあるそうです。
また、ワインには抗癌作用がある一方で、飲酒によって発癌リスクが上昇するという研究結果もあります。
つまり、飲み過ぎは良くないことがわかります。さらに、アルコールには食欲増進効果もあるため、ついついおつまみを食べ過ぎてしまうこともあります。ですので、適量を守って飲み過ぎに注意しましょう。
ただし、ワインは適切に飲めば私たちに多くの良い効果をもたらしてくれます。そこで、今回の記事を通じてワインに興味を持っていただけたら幸いです。
今回は以上です。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!